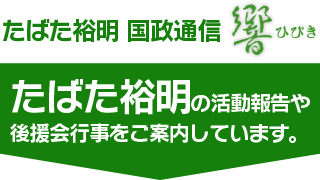たばた裕明の活動報告
活動報告
予算特別委員会質問要旨(6月22日午後1時~登壇)
本日(6月22日午後1時より予算特別委員会にて質問に立ちます。
以下、質問項目概要について掲載いたします。
大項目1 災害廃棄物受入れについて。
また私自身、厚生環境常任委員会における委員会質疑においても一貫して、放射能に汚染されていない災害廃棄物に限り、オールジャパンで復興支援する意味からも県内での災害廃棄物受けれ入れに前向きな考えで質疑を行ってきているもの。
(1)試験焼却の実施に当たっては、運搬、埋立も含め、県が仲介役としての役割を発揮すべきと考えるが、国と岩手県、受入れに前向きな基礎的自治体との役割分担はどうなっているのか、これまでの経過やその考え方とあわせて、問う。
(県内での受入れの検討状況について、県には、幅広く県民に対する情報提供を望む。)
(2)他県では、試験焼却後の焼却灰の最終処分場への埋立処理に関して、地元地域の住民への理解を深める説明会が丁寧に行われているが、県は、今後どのように対応するのか。
(焼却施設周辺と同様に、焼却灰の最終処分場の地元に対しても、住民説明がしっかり行われるべき。)
(3)受入れをすでに実施している静岡県では、環境省のガイドラインを踏まえ、静岡県独自の試験焼却に係る受入れ基準や全体計画を定めているが、試験焼却の結果の公表を含め、県では今後どのように対応するのか。
(4)今後、本格受入れに移行するとした場合、輸送に関して検討すべき事柄は何なのか、そのコスト負担の考え方を含め、問う。
大項目2 地域公共交通支援について
(1)生活バス路線については、通勤・通学者、高齢者、障害者等の日常生活に必要不可欠な移動手段であることから公費支援は必要だと考えるが、生活バス路線を維持するために、県はどのように取り組むのか。
(2)国交省では、エコ通勤優良事業所の認証制度を設け、環境負荷の少ない交通手段への転換を進めているが、今後県内事業所のエコ通勤の普及に県はどのように取り組むのか。
(3)既存JR駅の利用者増加策について、JR西日本と協働してどのように取り組むのか。
(JRの既存駅についても利用者は逓減状態である。経営分離前から利用者増加にむけて県としてもJRと連携して取り組んだり、基礎的自治体や地元交通事業者とも連携して鉄道利用者を増やすべきである。)
(4)JR高山本線についても、現状維持でなく、富山市と連携して利用者増加対策に取り組むなど何らかの対策が必要だと考えるが、今後どのように利用者確保を図っていくのか。
(高山本線に関しては、北陸本線の経営分離後もJRの直営でこれまで通りの営業となる予定である。)
(5)並行在来線新駅に関して、設置モデル地区の収支予測などが公表されているが、7つの新駅設置検討箇所の今後の取り扱いやそれぞれの地元地域の新駅設置推進組織の活動に対する対応について問う。
(6)新幹線富山駅の駅舎整備は、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の仕事だが、駅ビルテナントなど県都の玄関口の整備に関して県民の声はどのように反映される仕組みとなっているのか。
(7)新幹線の路線の通称・列車の名称、並行在来線会社の名称について、現在の県の考えを問う。
大項目3 子育て支援について
(1)本県における「認定こども園」設置数の推移と現状に対する評価を問う。
( 「総合こども園」創設は見送りとなり、「認定こども園」の存続・拡張で3党合意との方向のようだが、親の働き方に関わらず子どもを受け入れる幼保一体型施設の推進という方向性はこれまでの施策の流れと一致するものであり歓迎する。)
(2)県内の保育士、幼稚園教諭の質の向上のため、県はどのように取り組むのか。
(子どもにとって質の高い保育、教育が望まれているが、そのためには保育士、幼稚園教諭の質の向上が不可欠である。)
(3)事業所内保育施設のこれまでの設置状況を踏まえた評価と今後の課題について問う。
(事業主の設置ニーズに、国や県の助成制度はちゃんと応えきれているのか。)
(4)本県における児童の生活習慣病対策の取り組み状況はどうか、生活習慣病予防検診の実施状況と併せて、問う。
(県内の市町村間で取組状況にばらつきがあるのではないか。)
大項目4 ネオ屋台について
(1)本県で移動販売車、通称ネオ屋台を営業するにあたり、その許可の基準や規格要件はどうなっているのか。
(最近、移動販売車、通称ネオ屋台が県内でも増加傾向であり、スーパーの店頭入り口近くの駐車スペースや野外イベントでよく見かけ、盛況な賑わいづくりのツールとなっているが、車両や調理スペースの規格が全国各地でバラバラであると聞いている。)
(2)県内の厚生センターや富山市保健所によるネオ屋台の指導・監督の現状と県の今後の対応について問う。
最新記事
- たばた裕明、選挙も残すところ数時間のみとなりました。2024.10.26 up
- たばた裕明、選挙も残すところ本日のみとなりました。2024.10.26 up
- 本日は富山駅前CiC前広場にて、街頭総決起集会を開催させていただきました。2024.10.25 up